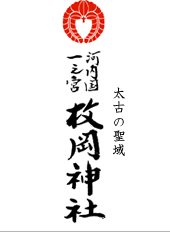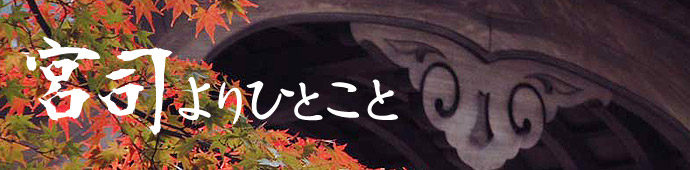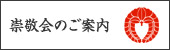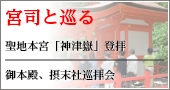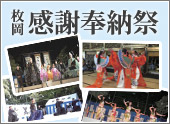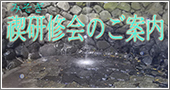枚岡神社のお笑い神事【更新日】平成23年12月1日
12月25日と言えばクリスマスを連想するのですが、この日、枚岡神社では笑いの神事がとり行われます。新しい年を迎えるにあたって、新しい注連縄を架けかえる「しめかけ神事」が午前9時から始まり、10時から「お笑い神事」が行われます。神代の昔、アマテラスオオミカミの岩戸隠れに際して、アメノコヤネノミコト(枚岡神社主祭神)の美しい祈りと、アメノウズメノミコトの踊りと、神々の笑いによって岩戸が開かれた故事によるもので、元にもどらないように縄を張ったのが注連縄の起源です。
笑うと細胞が甦り免疫力が高まる、病気や癌になりにくい、健康で若々しくなる、認知症になりにくい、夫婦円満になる、元気で長生きできる等々、その効果が広がっているせいか、年々参加者が増えています。当日、総代たちの手で注連縄が掛けかえられた後、宮司の「アッハッハッ」の音頭に続いて一同が「アッハッハッ」と、これを3度繰り返した後、全員で20分間自由に笑い続けます。
義務的に笑おうとしても、長時間笑えるものではありません。それにはコツがあるのです。それにはいいイメージを描くこと。例えば神仏に生かされている、有り難い、楽しい、嬉しい、美しい、気持ちいい、元気だ、等々いいイメージを描きながら笑うと、気持ちよく笑えて時間を感じないのです。白隠禅師も不治の病をこのイメージトレーニングで克服しました。
スポーツの分野では当たり前のこのイメージトレーニングを、日頃から稽古していると、あらゆる面にいい結果が生ずるのです。みなさんも是非挑戦してください。
早朝のボランティア【更新日】平成23年11月1日
枚岡神社に奉仕して早くも2年が経過いたしました。早朝から境内のお掃除をしてくださる氏子が7名いて、小生もこれに加わりました。ある落ち葉の多い朝、「今日は大変ですね」と、労いの言葉をかけましたら、「いえいえ、コガネ(黄金)を集めているので大変ではないです」と。なんと落ち葉を黄金に見立てて、喜んでご奉仕してくれているのです。
また、「今朝のトイレの汚れは大変でした」の言葉に、トイレのお掃除も知って、「それは大変だったでしょう」と言いましたら、「いえいえ、ウン(運)をつけているんです」と。なんと次元の高い徳のあるお方であろうかと敬服いたしました。その後境内に、「神さまに対する感謝の気持ちを、お掃除を通じてお返しすると共に、心の浄めと体の健康に努めましょう」と、掲示を出しましたら奉仕者が15名に増えました。
毎朝、掃き掃除をする人と参拝者との間で、「おはようございます」と、挨拶が飛び交う境内は、実に爽やかで気持ち良く、お陰で朝参りの数も増えてまいりました。落ち葉を農作に使う人もいますが、これが腐葉土となって豊作に繋がることを思えば、落ち葉はまさしく黄金とも言えるでしょう。また人の嫌がる不浄な所を綺麗にしょうとすることは、他の人に喜びを与え、徳が備わり、自分の内なる魂が磨かれ、次元が神さまのみ心に近づくことにもなるのです。
運命というものは、自分の行いによって刻々と変化いたします。境内のお掃除や人の嫌がるトイレの清掃、これらの日々の積み重ねが、その人に変化を与え、良い運がついてくるのです。
心と体の健康【更新日】平成23年10月1日
枚岡神社は生駒山の格好の登り口となっており、集合場所としても最適なせいか、ハイカーの姿が一段と目につきます。奈良時代、平城京から難波に通じる最短コースが暗越奈良街道で、その県境が通称「暗がり峠」。枚岡神社の神さまが春日大社に迎えられた由緒ある古道でもあり、それ故枚岡は元春日とも称され、枚岡の神さまが初めてお祀りされた神津嶽の聖地もあります。
ハイカーたちは境内に入っておりながら、お参りもしないでハイキング道に抜けてしまうので、たまりかねて次のような看板を立てました。「健康は歩くだけでは不十分で、内なる神気のよみがえりが大切です。先ずご本殿(正面階段上)で感謝の手を合わせてから歩きましょう。上からもハイキング道につながっています」と。
今年満百歳の日野原重明さんは、長年エスカレーターを使わず、階段を二段づつ上っておられます。2段づつ上ると腿の筋肉が鍛えられ、腿の筋肉は全身につながっているので、健康に良いと。足の筋肉が満ちみちておれば、病気になりにくく、幸せに過ごせるところから、「満足」という言葉が出来たとも言われ、筋肉を養う重要性から「貯筋」という言葉もよく使われています。
健康の「健」は体が健やか、「康」は心が安らいでいること。見える体の部分とその奥に隠れている心の分野も忘れてはなりません。言葉や想念も不思議な力があって、見えるモノに多分に影響します。感謝の手を合すと、体の奥に宿っている大いなる力が反応して、元気が甦ってまいります。
本来の物見遊山【更新日】平成23年9月1日
物見遊山という言葉は次元が低く捉えられています。そうでしょうか。モノという言葉には、目に見える唯物的な意味と、目に見えない唯心的な意味があるのです。モノノケヒメというアニメがありますが、モノノケとは見えない不思議な神秘な霊的な存在を意味しています。今の世はあまりにも目に見えないモノを否定し過ぎて、あらゆる面で行き詰まっているように思われます。
目に見える体の奥には目に見えない心があり、鬱や強度なストレスが続くと、目に見える体に影響いたします。われわれの体は臓器の寄せ集めであり、その臓器は細胞から出来ており、細胞は原子の組み合わせであり、原子をばらせば在るけれども見えなくなり、無限の宇宙とつながっています。超微細な細胞の中にも無限の宇宙が広がっているのですから、奥の奥にある生命というのは、まだまだ神秘な未知なる存在なのです。
先人は山や杜を神さまの領域として畏敬してまいりました。その結果命の水と清らかな空気が得られるのです。その命の水の湧き出る所に神々を祀って聖域を保持してきた先人に感謝し、一層聖域作りに励まなければ、努力を積み重ねてきた祖先に対しても、子孫に対しても申し訳ありません。
山に入って美しい木立や清らかなせせらぎを観て、その奥に隠れている大いなる力(神さま)を感じて楽しく遊ぶのが、本来の物見遊山なのです。21世紀は目に見える物と目に見えないモノのバランスをいかにとってゆくかでしょう。
世界に誇る大和言葉 <3>【更新日】平成23年8月15日
サとは稲の御霊。その苗がサナエ(早苗)、これを植える女性がサオトメ(早乙女)。稲の氣が入ったアルコールがサケ(酒)、神様の氣が入ったアルコールがミキ(神酒)。ミコシ(神輿)は神さまの乗り物。ミもヒと同様に神霊を意味します。
ケガレとは本来神様から戴いた氣が枯れてしまう事。幼児は戴いた神さまの氣が体に満ちみちているので、いつもエネルギュッシュです。年齢を重ねますと、しだいに戴いた神氣が枯れて病気になります。そこで神様の領域である山や杜に入って、神様の大いなる氣を戴いて、弱った氣を元の氣に返したのが元氣です。元には神さまの意味が含まれています。体の全ての細胞が2,3か月で新しく甦るように、戴いた神気も絶えず甦って、元気にならなければなりません。
神社の祭りやご祈祷には必ずヌサ(幣)でお祓いをします。白い紙をユウ(木綿)といい、これを結んだ茶色い紐をアサ(麻)といいます。アサもユウも古来より神聖な品として神事に使用されています。神聖な品で邪悪なものを祓ったのです。大事な役に当たっている神職の冠に麻の緒が結ばれていたり、装束の上に白い布(ユウタスキ)を着けているのを見たことがあるでしょう。これはより神聖になって神様に近づく姿なのです。
ユと同様、ユウもアサも神聖、ヒは神さまの御霊。美しいユウヒ(夕日)を見て神さまを感じ、差し昇るアサヒ(朝日)を見て神氣を感じて手を合わせて来た、我々の先人は実に感性が高く、高度な次元を持っていたのです。
世界に誇る大和言葉 <2>【更新日】平成23年8月1日
ヒラオカ(枚岡)のヒは神霊、ラは複数を意味します。ハは物を生み出す力。ハ(歯)で食物を噛むとエネルギーが生まれます。女性は赤ちゃんを生み出す大いなる力があるのでハがもう一つ加わってハハ(母)というのです。ハラ(腹)は赤ちゃんを育てる力がたくさんある所だからハラ。ヒラオカとは神霊がたくさんある岡、すなわち神気が満ち満ちた所なのです。
実際境内に入りますと山の木立が清々しくて、気分がよく、元気が漲ってまいります。キ(木)は命に欠かせない酸素を出して私たちを生かしてくれています。したがってキ(木)は私たちの命を育ててくれる神さまのキ(氣)そのものです。中でも榊は常緑で目出度く、栄えるという言葉とも繋がって、古くから神木として祭礼に使われてまいりました。因みに神様の数え方は一柱二柱と数えます。神主さんが奏上している祝詞も、古くから使われている大和言葉です。その中にユニワ(斎庭)という言葉があります。ユとは神様の居る「神聖」という意味。神聖な庭がユニワです。ウブユ(産湯)というと若い人たちは、生まれた赤ちゃんを湯で清潔にする、としかイメージしないのですが、もっと深い意味があるのです。すなわち生まれた赤ちゃんが神聖なユ(湯)で禊をして、人生の第一歩を踏み出す神事をしているのです。納棺前に遺体を湯でふき清めるユカン(湯灌)があります。
今はお葬式と言えばお寺、お坊さんをイメージしますが、仏教がわが国に入ってくる前は、皆わが国の風習、あえて言うなら神式でミタマ祭り(葬儀)をしておりました。亡くなれば神様の国へ帰って行くので、神聖な湯で禊をしているのが湯灌で、これも神事なのです。
世界に誇る大和言葉 <1>【更新日】平成23年7月15日
日本に帰化したリービ英雄氏が数年前に、『万葉集』という写真集を刊行されました。松岡正剛氏の書評には、「アメリカ人の彼が日本語に興味をもって勉強するうちに、古い大和言葉に行き当り、その一語一語に深い意味を持っている事がわかった。万葉集も大和言葉で詠われているので、これは世界の宝だ、と言う事で万葉集を出版された」とのこと。
わが国は太古から神代文字や記号文字があったと言われています。また、世界最古といわれる楔形文字は、わが国に一番多く残っているところから、日本で作られて世界に発進されたと言う説もあります。けれども一般的には、中国から漢字が入って来るまでは、わが国は文字がなく、言葉で意思疎通をはかっていたと言われています。それが大和言葉で、大和言葉には一語一語に意味があるのです。例えばヒカリという言葉。私達が日頃何気なく使っていますが、ヒとは神霊、カリは籠もる、という意味があります。美しい光の中に、神さまがいらっしゃるという思いから、ヒカリという言葉が出来ているのです。
私たちは太陽の力なしでは生命は生まれません。したがって太陽の力も、神様として称えられて、おヒ(神霊)さまと言います。私たちの体はただの物ではありません。体の奥深いところに神秘な無限の力が宿っているのです。それで男の子はヒコ(彦)、女の子はヒメ(姫)と言うのです。ヒ(神霊)が体に止まっているからヒト(霊止)。神様に相応しい行いをする者がヒト(霊止)で、そうでないのがヒトでなしなのです。
ワルシャワ大学の日本学科【更新日】平成23年7月1日
ポーランドのワルシャワ大学に日本学科があり、7,8年前に同大学でわが国の文化を教えているポーランド人が日本に来られました。なぜこの学科が出来たのかお尋ねしたところ、弱肉強食の時代であった100年ほど前に、陸海軍共に最強を誇るロシアと隣接するトルコやポーランドは、それに対抗出来ず戦々恐々としていた。そんな折に明治維新からまだ30余年しか経っていない極東の小国が宣戦布告をした。陸海軍世界最強のロシアに勝てるはずがない。愚かな可愛そうな民族と思っていたところ、陸軍でも勝利し、名高いバルチック艦隊にも完勝して世界中を驚かせた。なんという民俗なのか自国のためにも調べよう、というわけで日本文化を勉強する学科が出来たと言う。
それから100余年たち、一昨年は24倍という大学で1,2の人気ある学科になっているそうです。なぜ日本に来られたかというと、日本文化を研究していると必ずその根底に神道というものが見え隠れしているので、これを勉強したいと。我々の祖先は縄文文化を築き上げ、四季の移ろいの中から、自然の営みをキャッチする繊細な能力を身につけ、自然の奥に潜む不可思議な存在をカミと称して敬い、生かされていることに感謝と祈りささげてまいりました。
そのような次元の高い観念が失せてしまったのは、戦後の左かかった偏重教育の影響で、物と金しか考えない次元の低い民族に成り下がり、あらゆる面で行き詰っています。このような時こそ原点に立ち返り、先人が培ってきた智慧に触れるとき、新しい道が開けるのです。
民俗の移動と生駒山【更新日】平成23年6月15日
人類の起源は遥か600万年前に遡り、アフリカに誕生したといわれています。やがてアフリカ大陸を出てユーラシアに到達し、長い年月をかけて日出る東へ東へと移動するのは自然の流れです。1万5千年前は氷河期で海面は低く、日本列島は大陸と繋がっていたので、人も動物も陸続きにたどり着けたのです。その頃、日本海は大きな湖のような状態で、瀬戸内海も海ではなく、大きな川であったことが考古学的に判明されています。やがて水面が上昇し列島が分離しても、順次色々な民俗が渡って来て、各地に王朝を作ります。
ヤマトは比較的日本の中央にあり、盆地は湿地帯として米作りに適し、取り巻く青垣山は砦としても、また人々に欠かせない水と、金鉱が産出することから、国を治める立地条件に叶っていたのです。カンヤマトイワレヒコノミコト(神武天皇)が九州から瀬戸内海を通り河内の国から暗がり峠を越えて、一挙に大和に入ろうとしたのも、その情報があったからでしょう。大陸から各種の技術を持った民俗がこの地で集合し、急斜面の流れに動力源としての水車を設けて物作りが栄えていったのが枚岡の地域で、その貴重な水の湧き出る所が枚岡神社なのです。
生駒山の奈良県側は比較的なだらかなのですが、西側の大阪方は急斜面で、山の水が一挙に麓へ流れ落ちます。そんなところから「水走」という名前が付いたのでしょう。因みに地名は「みずはい」と読み、太古から幕末まで代々枚岡神社をお守りしてきた社家の水走家は「みずはや」と読んでいます。
日本建国と枚岡神社【更新日】平成23年6月1日
わが国の文化は神話と繋がっています。「自国の神話を忘れた時、その国は100年足らずで滅びる」とトウィンビーは言っていますが、わが国が神話を忘れて65年がたちました。人々が古い歴史と伝統を忘れて、根無し草となって混迷している今こそ、祖先の遺した偉大な智慧や文化を見直さなければなりません。
遥かな昔、カンヤマトイワレヒコノミコト(神武天皇)が九州から大阪に来られました。当時大阪平野は海で、たくさんの島がありました。都島や福島は当時の島の一つで、潮の流れが速かったことから、浪速(なみはや)の国と名づけられました。当時大阪湾を取り巻く一帯が河内の国で、奈良時代に摂津、和泉、河内の三つに分かれましたが、それまでは河内大国と言われていたのです。ミコトは最短コースの生駒の暗がり峠を越えて、大和に入ろうと浪速の港から河内大国に向けて船出をした所から、大国町の名が残ったと言われています。
ミコトは生駒の日下に上陸しますが、ナガスネヒコの阻止に遭い、困難を極めます。そこで早く国が平定出来ることを祈念して、祭りと祈りでもって天の岩戸を開かれた天児屋根命(枚岡神社主祭神)を神社の後方、神津嶽にお祀りされました。その後迂回して熊野から大和に入り、橿原の地に建国されて今年は2671年になります。その3年前に枚岡の神様がお祀りされたので、当社は日本有数の古社として称えられているのです。
東日本大震災によせて【更新日】平成23年4月15日
去る3月11日、14時46分にM9.0という未曾有の巨大地震が発生しました。この震災によってお亡くなりになられました方々に衷心より哀悼の意を表しますと共に、一日も早い復興を願って、当社では毎朝のお祭りに祈りを捧げております。また早速物資をお送りすると共に、境内で義捐金の募集を行い、甚大な災害を蒙りました神社界への支援として職員はもとより、崇敬会や当社の関係諸団体にも呼びかけております。
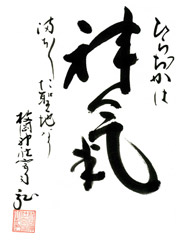
この日私は所用があって上京しておりました。列車は全線不通となり、いつ来るかわからないタクシーも長蛇の列で、寒風の中をひたすらさまよい、何とかホテルに投宿することが出来ました。ホテルに入ってからも何度も余震があり、テレビの画面に映し出された想像を絶する光景に、ただただ驚くばかりでした。津波によって家屋や車が玩具のように流されてゆく信じられない状況に、大自然の威力と人間の無力さを感じざるを得ませんでした。地震、津波、火災、これに加えて原発事故。これまで経験したこともない災難が一度にやってきたのです。
我々の先人は太陽はもとより、土や水、草や木に対しても、人智では計り知れない不思議な力を感じて、それをカミという表現で敬意を表してまいりました。人はより便利な物を次々にこしらえて享受してゆくうちに、物さえあれば100%幸せであるという錯覚に捉われ、大切な心の分野をないがしろにしてきたように思われます。
科学が進めば進むほど見えない分野に到達し、生きとし生きるものの命がいかに奥が深くて、神秘でわからない存在であるか、そしてそれらの命がみなつながっている、ということがわかります。また今まで思い通りに物が手に入っていたのが、一変して手に入らないことに気づきました。あらゆる物に対して敬虔な心、感謝の心を捧げてきた祖先の智慧を、学ぶべき時がきているのではないでしょうか。いまだに世界のどこかで紛争がおこり、人々の欲望は止まるところを知りません。それとともに自然環境も年々悪化し、全ての面に行き詰まっているように思われてなりません。このまま世界の人々が貪欲に突き進めば、早晩地球はくいつぶされてしまいます。人々の生き方、物の考え方がいい方向に転換し、日本の国が再生されて世界の国々からまた称賛されることを願うばかりです。